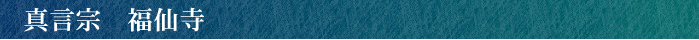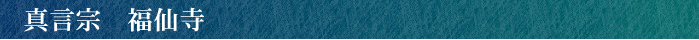(画像は【 click!】で拡大表示:二度クリックでさらに拡大) (画像は【 click!】で拡大表示:二度クリックでさらに拡大)
仏教事典では、
地蔵菩薩 (じぞうぼさつ)、サンスクリット語クシティ・ガルバは、仏教の信仰対象である菩薩の一尊。クシティは「大地」、ガルバは「胎内」「子宮」の意味で、意訳して「地蔵」と言う。また持地、妙憧、無辺心とも訳される。*1.三昧耶形は如意宝珠と幢幡(竿の先に吹き流しを付けた荘厳具)、錫杖。
大地が全ての命を育む力を蔵するように、苦悩の人々をその無限の大慈悲の心で包み込み、救う所から名付けられたとされる。一般的には「子供の守り神」として信じられており、よく子供が喜ぶお菓子が供えられている。
*1.三昧耶形 (さんまやぎょう/さまやぎょう)とは、密教に於いて、仏を表す象徴物の事。三形 (さんぎょう)とも略称される。
ちなみに三昧耶とはサンスクリットで「約束」、「契約」などを、意味するサマヤから転じた言葉で、どの仏をどの象徴物で表すかが、経典によって予め「取り決められている」事に由来する。
伝統的には、如来や菩薩などの仏の本誓、即ち衆生を救済するために起こした誓願を、示したものと定義される。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
一般的に、親しみを込めて「お地蔵さん」、「お地蔵様」と呼ばれます。
境内にはこのお地蔵さんと、水掛地蔵・御堂の中のお地蔵さん・の三体が祀られています。
地蔵と閻魔は裏表です。
地蔵と閻魔は一(いつ)と言います。
それは、地蔵は慈悲を、閻魔は忿怒(ふんぬ)をあらわし、全く反対の存在のようにみえるが、共に阿弥陀仏の分身であるということを言います。
生死も裏表、
生死一如(しょうじいちにょ)
仏教では、「生」と「死」を別のものとして分けてとらえることはしません。二つをひっくるめて「生死(しょうじ)」といい、生死の差別(しゃべつ)を超えることを説いています。つまり、生があるから死がある。生の中に死があり、死の中に生がある。したがって、人間は、死にたくなくても、いつかは死ななければなりません。だからこそ、命ある限り精一杯生き、そして死んでいくのです。
「死にたくない」そのことにこだわらず、現世を懸命に生き抜いて、死んでいく。そして、いざ死を迎えるその時には、死に方にもこだわらない。立派な死に方をしようと、格好をつける必要はないのです。死に方よりも、むしろ死を迎えるまでの、生き方が問題と言えるのでは…
人間は、自分の意思で、生まれてきたのではないのと同じように、自分で死に方を選ぶことはできません。いつどんな死に方をするかは、誰にもわかりません。それ故、生き方が大切なのです。どう生きたらいいのか。誰かに聞いても教えてくれません。自分でみつけようとする心を念頭に、水のように、雲のように自由で、自然で柔らかい心で、生きて行くことでいいのだと思います。
一休禅師の「死ぬ時節には死ぬがよく候」…諦めよといいます。諦めとは仏教用語です。
自分の出会う死という『無常の現実』を明らかに観る。そのことを人は、黙って受け入れる他はありません。
『(無常)を明らかに観て(諦めて)受け止める」それが肝心なのです。仏教の根幹はこだわりを捨てること。財産や名誉はもちろん、最後は命に対するこだわりも捨てなければなりません。
△〜▽=△=▽=△=▽=△=▽=△=▽=△=▽=△=▽=△=▽=△=▽〜△
次に生死観について、
西洋での生死観は、生と死の世界を、断絶したものととらえるようですが、仏教の伝統的な生死観は、連続の関係であり、人は緩やかなプロセスを経ながら、あの世にたどり着くというのが、日本人の伝統的な生死観です。
それには具体的に、初七日・四十九日忌・命日・一周忌・その後の年忌と、死者を定期的に敬い弔う、仏教のしきたりが一番です。
死がすべての終わりでなく,人が亡くなっても、死者と生者の繋がり続くと考える方が、亡くなってゆく本人にとっても、見送る遺族にとっても、精神的には健全だと思います。
誰にでも訪れる死は、人間にとって「究極の平等」です。人が亡くなっても、生者と死者のつながりは、続くという知恵に、救いが感じられるはずです。
身内の死に立ち直るまでに、何年もかかる人もあれば、数日で落ち着く人と、さまざまのようです。
気持ちを立て直すために、大事な思い出とともに、早く新たな一歩を踏み出すことに努めることです。
生と死は、コインの表と裏のようなもの。
同じように、死の準備を全くせずして、真に人生を明るくさせることは、不可能なのです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
お釈迦様は、自らの入滅に臨んで、嘆き悲しむ弟子達に「諸々の事象は移りゆく無常の世界、汝ら怠ることなく努力せよ」と遺言されました。
又弘法大師の遺された教王教開題の一節に、
「そもそも生は、自ら願って得たものではなく、根源的な無知を父として、私達はこの世に生を享(う)けたのである。ましてや、死は私達の望む所ではないけれども、死の報いをもたらす原因と、行為との無情な鬼がやってきて、私を殺す。生は必ずしも楽ではない、諸々の苦しみが集まるところである。死も決して喜ばしいことではない、諸々の憂いがたちまちに迫ってくる。生まれたのはつい昨日のようであるけれども、たちまちに髪に霜をおく。強く壮(さか)んなのも今朝のこと、明日の夕方には病を得て死んでしまう。…この身のもろく儚(はかな)いことは、水の泡のようであり、我が命に実体がないことは、夢や幻のようである。…あァ〜なんと悲しいことであろうか、すべての世界の生死のはざまに流転する者は…あァーなんと苦しいことであろうか。六つの迷いの世界(六道)の間を、輪廻転生する者は。仏教の真理に、よく通じている菩薩の優れた教導の力、みほとけの人々に向けられる、大いなる憐れみの功徳の力に頼まなければ、どうして良く生死の海に、流転する働きの輪を破って、永遠の悟り(仏果)の座に登ることが出来るだろうか」として、お釈迦様もお大師様も、自己そのものが無常という人間の真相から、目をそらすことなく、悟りの道に怠ることなく努めよと、諭されていることが、このことからも理解出来ます。
死は悲しい人生の真相であるが、その死の悲しみを乗り越える道こそ、人生最大の課題です。
<やがて死すべき身の
今命あるは尊し>
石地蔵の〓余談〓
昔、田舎の結婚式は、多く自宅でしていました。
当時田舎の近所の若い衆が、路傍の石地蔵さんを、婚礼の席に持って行って、据える習慣がありました。戦後しばらく、この風習が残っていました。
石地蔵さんを婚礼の席に据える理由は、嫁に来たお嫁さんが、永くその家に石地蔵さんのように、居座ることを願ったのです。また二人がいつまでも、この地、この家で腰をずっしりと据え、仲よく、そして家の繁栄、子孫繁栄の為にと願ったのです。村の若い衆がやがて生まれてくる、二人の子供の成長を、お地蔵さんに願っての風習だったのだと思います。
石地蔵さんを、持ち込んだ若い衆は、その家からその席で、ご祝儀、御馳走、お酒を振る舞われました。翌日若夫婦は、その石地蔵さんを、元の場所に戻しに行ったのです。先ずそれを協同の初仕事にして、新婚生活が始まったのです。
*******************************
|