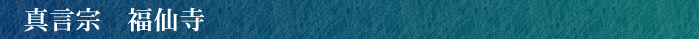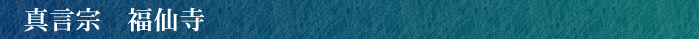当山の超々小型の愛染明王(極小ミニチュア)で(超絶技巧の愛染明王像)=製作年代は不明です。極小像としての工芸的価値。 当山の超々小型の愛染明王(極小ミニチュア)で(超絶技巧の愛染明王像)=製作年代は不明です。極小像としての工芸的価値。
=《 ※【画はクリックで拡大】※ 》今度画は差し替えます。
「念じ持つ仏」=「ねんじぶつ」・信仰の対象として常に念じ、身近に持つ仏像。
超絶技巧の造形:数センチ程度のサイズにもかかわらず、細部まで忠実に再現。密教的迫力と技巧が凝縮。美術的価値:仏像彫刻の技術的粋が詰まった作品であり、単なる観賞用模型ではなく、宗教的・芸術的対象だと思います。単なる「フィギュア=玩具」ではありません。知る限りでは、宗教的・芸術的対象に当たる極小愛染明王像です。
愛染明王とは、煩悩や愛欲を浄化し、正しい生命力へと転化する密教の極意を体現させるとされる、一面三眼六臂の忿怒形で、獅子冠を戴き、弓矢を持つ姿が特徴です。この極小像でもその造形は忠実に再現され、台座には宝瓶などの密教的意匠が施されています。
何時造像されたのか分かりませんが、極小ながら密教的な迫力と精緻な造形を備えています。
愛染明王は、一面六臂が基本形で、獅子冠を戴き、蓮華上に坐す。恋愛成就や人間関係の円満を祈願する仏として、江戸時代以降は庶民にも親しまれる
一面三眼六臂の忿怒形:怒りの表情で煩悩を打ち砕く力を象徴。三つの眼は過去・現在・未来を見通す智慧を示す。
・獅子冠を戴く:獅子は王者の象徴であり、威厳と守護の力を表す。
・弓矢を持つ:煩悩を射抜く武器としての意味を持つ。
・蓮華上に坐す:蓮は清浄の象徴であり、煩悩の中にあっても清らかであることを示す。
・台座に宝瓶などの密教的意匠:宝瓶は智慧や福徳の象徴であり、台座全体が密教的世界観を表現。
以下AIから、
ミニチュア像としての魅力があります。
・極小サイズでも精緻な造形:細部まで忠実に再現されており、密教的迫力と技巧が凝縮されている。
・超絶技巧の工芸性:仏像彫刻の技術的粋が詰まった極小作品であり、美術的価値も高いと思います。
「フィギュア=おもちゃ」との違い。
「フィギュア」とは?
・定義:人物やキャラクターなどの立体模型。観賞用・収集用が主。
・目的:鑑賞、コレクション、時に芸術的価値。
・特徴:
・精密な造形や彩色
・アニメ・ゲーム・映画などのキャラクターが多い。
・可動式のものもあるが、遊ぶより飾ることが主眼。
・例:
・ガンダムのプラモデル(ガンプラ)
・美少女キャラのスケールフィギュア
・ 特撮ヒーローのアクションフィギュア
違いのポイント
たとえば「ウルトラマンのソフビ」は子ども向け玩具ですが、「精密造形のウルトラマンフィギュア」は大人向けコレクターアイテムです。境界は曖昧で、両方の性質を持つものもあります。
煩悩即菩提のこと、
出典: フリー百科事典『ウィキペディア』
煩悩即菩提(ぼんのう そく ぼだい)は、大乗仏教の概念の一つ。
生死即涅槃と対で語られる場合が多い。
悟り(菩提)とそれを妨げる迷い(煩悩)とは、ともに人間の本性の働きであり、煩悩がやがては悟りの縁となることである。
概要
原始仏教においては、煩悩を滅することに主題がおかれ、それにより覚りが得られるとされていた。
しかし、時代を経て大乗仏教の概念が発展すると、すべての衆生は何かしら欲求を持って生活せざるを得ず、したがって煩悩を完全に滅することは不可能と考えられるようになった。また煩悩があるからこそ悟りを求めようとする心、つまり菩提心も生まれると考えられるようになった。
したがって、煩悩と菩提は分けようとしても分けられず、相(あい)即(そく)して存在する。これらのように、二つであって、しかも二つではないもののことを而二不二(ににふに)という。これは維摩経に示される不二法門の一つでもある。
般若心経に「色即是空 空即是色」とある通り、この色(しき、物質的)の世界は、固定した実体や我がない空であり、それ自体がすべて真如のあらわれである。さらに、この空の世界が、そのままこの世に存在するすべてのものの姿である。したがって、煩悩の概念そのものがなければ、相対的な悟りの概念もない。また、悟りも悟りを妨げる煩悩もその本体は真実不変の真如のあらわれである[10]。それゆえ、煩悩を離れて菩提は得られない。また逆に、菩提なくして煩悩から離れることはない。これを「煩悩即菩提」と言う。
なお、煩悩即菩提といえば、相対した矛盾する言葉が「即」でつながっていることから、「煩悩=菩提」、煩悩がそのまま悟りである、と考えられやすいが、これは誤解であり、間違いである。天台本覚思想に走れば、現実の相対的二元論を忘れ、而二不二の考えを忘却し、本覚思想の絶対的一元論より「煩悩そのまま菩提」という風に直接肯定してしまうことになり、人々の愛欲や煩悩を増長し、退廃し、墮落することになるため、誤った解釈である。あくまでも紙一重、背中あわせで相対して存在しており、煩悩があるからこそ苦を招き、その苦を脱するため菩提を求める心も生じる、菩提があるからこそ煩悩を見つめることもできる、というのが煩悩即菩提の正しい語意である。
|