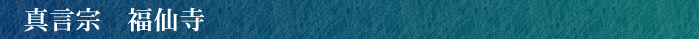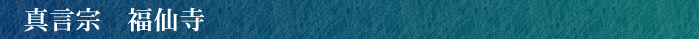(画はクリックで拡大) (画はクリックで拡大)
檀紙(だんし)という紙は、現代では一般に用いられていませんが、調べてみると、昔は品位が高いとされていた儀礼用の和紙で、
『正倉院文書』にもこの紙名があり、すでに奈良時代に存在し、平安から鎌倉時代にかけては上流社会で広く愛用され、当時の文学作品にもしばしば出ていたそうです。
一説では、檀紙は真弓の紙(まゆみのかみ)ともよばれたようです。
百科事典で「檀紙」を調べると、
真弓(まゆみ) マユミ (ニシキギ科ニシキギ属の木) 別名ヤマニシキギの表皮を剥いでコウゾウ紙と混ぜて漉く紙のようです。
古くは主に、弓を作る材料であったニシキギ科の落葉亜喬木であるマユミ(檀/真弓)の若い枝の樹皮繊維を、原料として作られたためにこの名があります。
この寄進状の紙が檀紙です。
観應3年・正和3年。
(共に南北朝時代≒貞和の後、文和の前1350年から1351年)の寄進状が檀紙です。
少しごわっとした手触りで、丈夫な紙です。
長享の年号の檀紙は、
1487年から1488年までの期間を指していて、この時代の天皇は後土御門天皇・室町幕府将軍は足利義尚の時代と言う事です。
明和八年のもありますが、
明和年間は、災害が相次いで起こり、特に「明和九年は迷惑年」などと言われたそうです。
「明和九年」≒「迷惑年」で語呂合わせになります。
(檀紙≒コウゾを主原料に マユミ(真弓)を混用して漉かれた紙)
・・・只今書き込み中・・・
項目(画面)を替えるには、
マウスポインタで、左方上部隅に有る「戻る」をクリックして下さい。
|